「運用保守エンジニアって、夜勤やシフト制が大変そう…」
そんなイメージを持っていませんか?
転職やキャリアチェンジを考えている方にとって、「自分の生活がどう変わるか」という勤怠事情はとても大きな判断材料になります。
実際、私も未経験からこの仕事を始めるときに、夜勤がある働き方に不安を感じていました。
でも、今だから言えることがあります。
💡夜勤やシフト制の働き方は、確かに楽ではない。だけど、それだけで敬遠するのはもったいない。
この記事では、現役の運用保守エンジニアとしてのリアルな経験をもとに、
- シフト制の実態
- 夜勤での業務内容
- 生活リズムの整え方
- 向き不向きの判断基準
などを具体的に解説します。
不安を抱えるあなたのヒントになれば幸いです。
目次
シフト制の実態|スケジュールは?休みは取りやすい?

2交代・3交代制の具体例
運用保守の現場では、以下のようなシフト体制が多く見られます。
- 2交代制:日勤(9:00〜21:00)と夜勤(21:00〜翌9:00)を交代
- 3交代制:早番(8:00~16:00)・遅番(16:00~24:00)・夜勤(24:00~8:00)の3パターン
実際の勤務スケジュール例(体験談)
私が所属していた現場では、2交代制が適用されていました。
以下のようなスケジュールが例です。
| 月 | 日勤 |
| 火 | 夜勤 |
| 水 | 明け休み |
| 木 | 夜勤 |
| 金 | 明け休み |
| 土 | 休日 |
| 日 | 休日 |
このように、夜勤明けが休み扱いになる場合もあり、週に3〜4日オフになることもあります。
希望休・有給の取りやすさ
「シフト制だと休みが取りにくいのでは?」と不安に思うかもしれませんが、チーム内で調整できる現場であれば希望休も比較的取りやすいです。
ただし、人員に余裕がない職場では希望休が通りにくいこともあるため、転職活動の際には確認しておきましょう。
夜勤対応のリアル|本当に寝られる?何をしているの?

夜間の主な業務内容
夜間に実施する作業は具体的に以下のようなものがあります。
- アラート監視
- バッチ処理やバックアップの監視
- 夜間メンテナンス対応
- 定型レポートの作成など
仮眠の実態
現場によっては、仮眠時間がルールで定められている場合もあります(例:深夜1:00〜3:00の間に60分)。
ただし、障害発生時は対応を優先する必要があるため、仮眠=確実に寝られるとは限りません。
「寝られたらラッキー」くらいの意識が現実的です。
夜勤で崩れがちな生活リズム、どう整える?
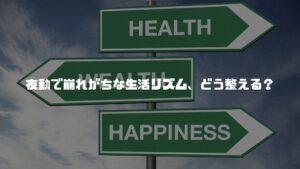
夜勤明けの過ごし方(私の例)
私のパターンをご紹介します。
- 帰宅後すぐシャワー
- 軽食をとって3時間程度の仮眠
- 昼過ぎに起きて軽く活動
- 夕方から2時間ほど仮眠して夜勤に備える
このように、昼と夕方に分けて寝ることで、疲労を分散させていました。
睡眠・体調管理の工夫
- 遮光カーテンと耳栓で日中でも睡眠環境を確保
- 寝る直前のスマホやカフェインを控える
- 夜勤中もこまめなストレッチで眠気防止
これだけでも翌日の体調がかなり変わってきます。
夜勤には“工夫”が必要不可欠です。
シフト勤務に向いている人・向いていない人とは?

向いている人の特徴
- 自分で生活リズムを設計できる
- 平日休みの利点を活かせる(役所・病院・観光地が空いてる)
- 静かな環境や単独作業が好き
向いていない人の特徴
- 朝型の生活リズムを絶対に崩せない
- 家族やパートナーと生活を合わせたい
- 睡眠の質が著しく落ちる人
体調を崩してまで無理に続ける必要はありません。
「少し合わないかも」と感じたら、上司や転職エージェントに相談するのも大切です。
まとめ
夜勤やシフト制は、身体的にも精神的にも簡単ではありません。
ただ、その分短期間で得られるスキルや経験も大きいのが事実です。
- 緊急対応の判断力
- 運用スキルの土台づくり
- 自分の生活を自分でコントロールする力
これらは、エンジニアとしての市場価値を大きく高めてくれます。
💡夜勤があるからといって、最初から選択肢を狭めるのはもったいない。
「自分に合っているかどうか」を見極めるためにも、まずは情報を集めてみてくださいね。

コメント